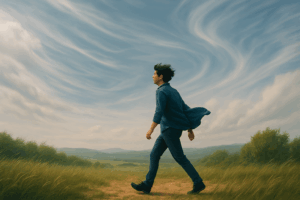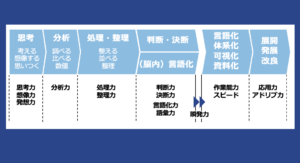前回の記事では、「思考を外に出すこと」の重要性についてお伝えしました。
頭の中の抽象的な考えを、紙や言葉として“外に置く”ことで、行動が生まれる。
そこまではできたけれど、いざ書き出してみると――
「情報が多すぎて整理できない」
「何から手をつけるべきか分からない」
そんな状態に陥る人も多いと思います。
今回のテーマは、その次のステップ。
外に出した思考を“構造化”して、関係性を見える形にすることです。
かたちが見えることで、関係が見えてくる。
その関係が見えることで、次の行動が自然に定まっていきます。
1. 「見える化」は“終わり”ではなく“始まり”
書き出す・話す・描くといった行為は、思考の“可視化”の第一歩です。
しかし、見える化しただけでは、まだ情報が並んでいるだけの状態。
整理しようとしても混乱が残るのは、関係性がまだ整っていないからです。
重要なのは、「要素」ではなく「つながり」を見ること。
混乱の原因は、情報の多さではなく、構造が未整理であることにあります。
思考を整理するとは、減らすことではなく、関係をつくることなのです。
2. 「関係」を見つける3つの整理軸
関係性を整理するためには、3つの軸を意識すると効果的です。
これを使うだけで、思考が一気に立体的になります。
(1)時間軸 ― Before → Now → Next
時系列に並べると、「今どの段階にいて、次に何をすべきか」が見えます。
“過去の背景”“現在の課題”“これからの方向”を並べることで、自然に流れが生まれます。
たとえば、
Before:アイデアを出した段階
Now:実際に動き始めた段階
Next:広げていく段階
というように整理すれば、「どこに課題が集中しているか」も明確になります。
(2)目的軸 ― Why → What → How
次に、目的と手段を分けて考えます。
思考が混乱しているときは、この3つ――
Why(なぜ)/What(何を)/How(どうやって)――
が一緒になっているケースが多いからです。
- Why(なぜ)=目的
これは、行動の「根拠」や「意味」を明確にする段階です。
たとえば「発信を増やしたい」の背景には、
“信頼を得たい”“自分の考えを広めたい”
“仕事の相談が増えてほしい”
など、
さまざまな理由(目的)が隠れています。
Whyを明確にすると、行動が
「やらなければならないこと」ではなく
「やりたいこと」に変わります。
- What(何を)=方向・中身
Whyが定まったら、「何を通じて目的を達成するか」を具体化します。
たとえば、信頼を得たいなら「実績紹介」や「考え方の共有」、
認知を広げたいなら「SNSでの露出」や「コラボ企画」など。
Whatは、目的を実現するための“具体的な内容”を決める段階です。
- How(どうやって)=手段・方法
最後に、「どのような形で実行するか」を設計します。
ブログで発信するのか、動画を作るのか、セミナーを開くのか――。
Howは、実行の“型”を定める段階です。
この3層を順番に整理するだけで、思考は驚くほど整います。
Whyが曖昧なままHowに進むと、方向がぶれたり、行動が続かなかったりします。
逆に、Why → What → Howの順で整理すれば、
目的と手段の一貫性が生まれ、行動の軸が強くなるのです。
(3)価値軸 ― 重要度 × 緊急度
これはビジネスでも使える万能な整理軸です。
重要だけど急がないことに時間を割くことで、長期的な成果につながります。
一方、重要ではないけれど急ぎのことに追われると、思考が散漫になります。
下図のように、「重要度 × 緊急度」で4つの象限に分けて考えると、
自分がどの領域の仕事に時間を使っているかが一目で分かります。
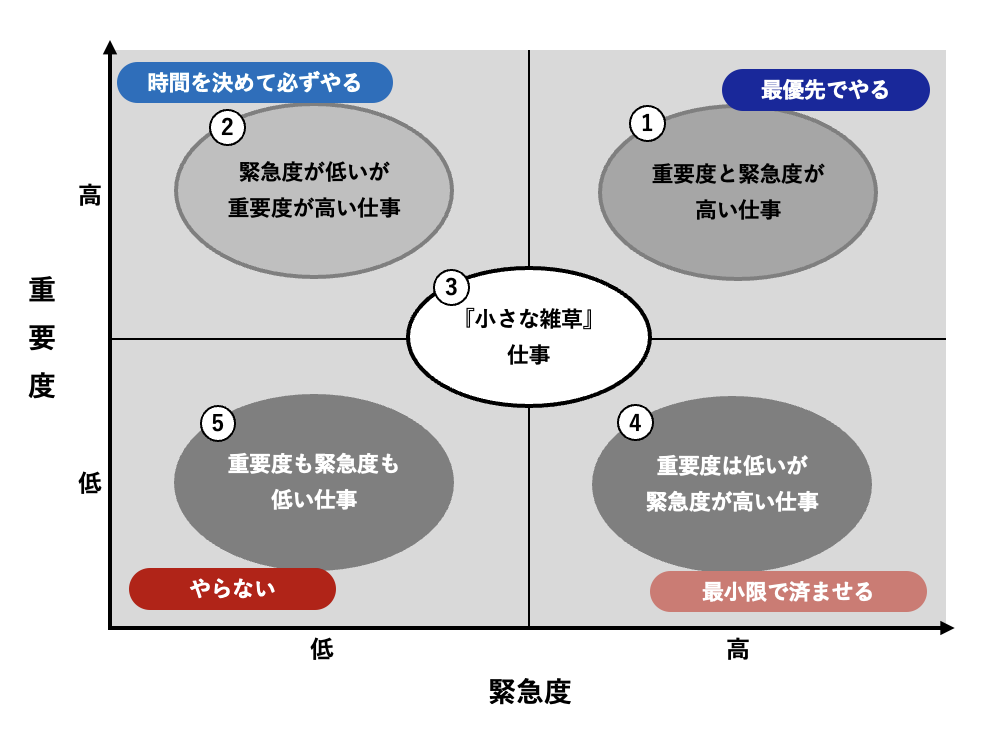
💡図の読み方
① 最優先でやる仕事(重要かつ緊急):期限が迫っており、成果に直結する仕事。
② 時間を決めて必ずやる仕事(重要だが緊急ではない):成長や仕組み化など、未来を作る仕事。
③ 小さな雑草仕事(どうしても発生する簡単な仕事):隙間時間でササっと片付ける。
④ 最低限で済ませる仕事(重要ではないが緊急):完璧を目指さず、最小限で済ませる工夫を。
⑤やらない仕事(重要でも緊急でもない):ムダな仕事。意識的に“やらない”選択をする。
日々のタスクをこのマトリクスに置いてみると、
「本当にやるべき仕事」と「やらなくてもいい仕事」が自然に見えてきます。
思考の構造化とは、単に整理することではなく、
“どこにエネルギーを注ぐか”を可視化することでもあります。
(詳しくは、過去記事:「1日を27時間に! 業務の最適化への道(2) 優先順位の必要性と手順」を参照。)
3. 構造化の手順 ― “俯瞰して・整理して・決める”
見える化した要素を構造化するには、次の3ステップを意識します。
① 俯瞰する
まず全体をざっと眺める。判断はまだしない。
あえて距離を置くことで、
「全体の中で何が起きているか」
を冷静に把握できます。
② グループ化する
似ている項目、関連している項目を近くに置く。
バラバラだった思考がまとまり始め、論点が整理されます。
③ 流れをつくる
矢印や線で関係をつなぐ。
「原因と結果」「目的と手段」「優先と補助」の関係が見えることで、
次のステップが明確になります。
このプロセスで、点だったアイデアが線になり、線が面としてつながっていく。
構造が見えることで、思考は“自然に動き始める”のです。
この3段階は、「思考の交通整理」にも似ています。
いきなり決めようとせず、まず全体を眺め、
関係を整えてから動くことで、ムダな衝突や迷走を防ぐことができます。
4. 「関係」が見えると、判断が早くなる
関係が見えるようになると、迷いが減ります。
たとえば、どのタスクを先にやるか、どの方向で進めるか――
判断に時間をかけず、自然に決断できるようになります。
構造が整っていると、判断の基準が明確になります。
「この要素が中心だから、ここを動かせば全体が進む」
「ここを後回しにしても影響が少ない」
そうした“全体を見渡す感覚”が身につくのです。
思考を構造化することは、意思決定の精度を高めることでもあります。
見えることで、判断が早くなる。
それが、思考を“動かす”ための第二段階です。
関係が見えるというのは、いわば「思考の地図を持つ」ようなものです。
どこに進むか迷っても、地図があればすぐに現在地と目的地を確認できます。
判断の速さは、情報量ではなく、構造の見通しで決まります。
5. 習慣化 ― 「構造図を残す」
一度整理した思考は、必ず“図として残す”ことをおすすめします。
その図は、単なる記録ではなく、“思考の地図”になります。
時間をおいて見返すと、
「あのとき何を考えていたか」
「なぜその判断をしたか」
が明確になり、
自分自身の成長を確認できます。
💡ツールは問いません:
紙のノートでも、ホワイトボードでも、デジタルでも。
重要なのは、“見える状態を保つこと”です。
思考の構造は、あなたの判断の軌跡です。
それを残していくことで、次の選択がどんどん速く、確かになっていきます。
また、構造図を残すことの、もうひとつの利点は、
「再現性」と「共有性」が高まることです。
同じような課題に直面したとき、過去の図を見返せば、思考プロセスを再利用できます。
また、チームやパートナーと共有する際も、図があるだけで説明の時間が半分になります。
6. まとめ ― 「見える」は、思考の循環をつくる
思考は、「出す → 見る → 整える」で循環します。
“見える化”はその中心にあり、
思考の滞りを解消し、前進のエネルギーを生み出します。
書いて、並べて、関係をつかむ。
それだけで、頭の中の霧が晴れ、道筋が見えてきます。
思考を動かすとは、見える形にすること。
その先に、次の展開が生まれます。
次回は、今回整理した“構造化された思考”を、
どのように「戦略」や「計画」に変えていくかを扱います。
テーマは、
「構造を戦略に変える ― 計画の筋道を描く」
思考を形にした先に、どう設計し、どう進めていくのか。
“動かすための構想術”を具体的に解説します。
ーーーーーーーー
【関連記事】
過去記事:「焦りを手放し、心と思考を整えるーー 何もしない時間が未来を動かす理由」
「 “整った自分”で選ぶ ― 納得に基づいて次の一手を見極める」
「 “整った自分”で決める ― 戦略としての決断を形にする」
外部記事(note):「思考をかたちにするーー見えることで、動き出す」
*
*
オンライン相談
オンライン相談
1回90分 11,000円 いまなら5,500円(税込)
ひとりで考えていても答えが出ない。けど、相談できる相手がいない・・・
そんな悩みを、気軽にご相談ください!
・申し込む前に、もう少し詳しい情報が欲しい
・自分のケースが当てはまるのか知りたい
など、ご要望のあるかたは、『お問い合わせフォーム』から、お気軽にご連絡ください!