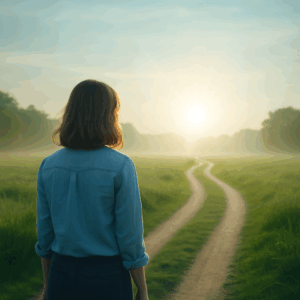前回の記事では、「思考を構造化する技術」についてお伝えしました。
情報を整理し、関係を見える形にすることで、思考が動き始める。
今回はその“構造化された思考”を、実際に戦略や行動計画に変えていく段階です。
「見えるようにはなったけど、次にどう動かせばいいのか分からない」
そんな段階に立っている人に向けて、
“流れを設計する”=構想を実行へつなぐ技術をお伝えします。
1. 戦略とは、“構造を動かす設計図”
構造化によって全体像が見えたら、次は「進む順番」を決める段階です。
戦略とは、言い換えれば“構造を動かす設計図”。
戦略=どの順番で、どこにエネルギーを集中させるかを決める思考
計画=戦略を時間軸に落とし込んだもの
この2つを混同すると、行動がブレます。
戦略は「方向性と優先順位」を決めるもの、
計画は「具体的な行動スケジュール」に変換するもの。
たとえば、
・戦略:サービスAに集中して事業の柱をつくる
・計画:3か月で新サイト公開、1か月後に検証
このように分けて考えることで、全体像が明確になり、実行の軸がぶれなくなります。
2. 「戦略」をつくる3つの視点
(1)目的(Why)に立ち戻る
戦略を立てるとき、最初に確認すべきは「なぜそれをやるのか」。
行動レベルではなく、“成果”として何を成し遂げたいのかを明確にします。
目的が曖昧なまま進むと、努力の方向がズレ、やる気も長続きしません。
Whyを明確にすることは、戦略を“生きた構想”に変える第一歩です。
(2)資源(リソース)を見極める
戦略は「理想」ではなく「現実」からつくるもの。
時間・人・予算・スキル・情報――
使えるリソースを正確に把握することで、
実行可能な戦略が見えてきます。
「今あるもので、どこまでできるか」
「足りないものを、どう補うか」
ここを見誤ると、戦略は絵に描いた餅になってしまいます。
(3)順序を決める(シーケンス設計)
次に、「どの順番で動かすか」を決めます。
すべてを一度に動かそうとせず、
“今やること”と“あとでやること”を明確に分けることが重要です。
判断の軸はシンプルです。
・すぐできるか
・効果が大きいか
・継続できるか
この3要素を基準にすれば、優先順位が自然に見えてきます。
戦略の本質は、“選ぶこと”よりも“捨てること”。
限られた資源を、最も効果のある場所に集中させることが、戦略の核心です。
3. 「計画」に落とし込む3ステップ
構造化された思考を戦略に変えたら、次はそれを「計画」に落とし込みます。
その流れは、次の3ステップで十分です。
① 構造図をベースに、優先度の高いブロックを選ぶ
全体図の中から「今すぐ動かすべき」部分を抜き出します。
② 各ブロックに“目的・手段・期限”を設定する
何のために・何を・いつまでにやるのかを、明文化します。
③ 時間軸に沿って配置する(週・月単位)
ToDoリストではなく、“流れ”としての計画にすることがポイントです。
💡例:
ブロックA:新サービス設計 → 今月中
ブロックB:SNS戦略 → 2週間で試験運用
ブロックC:顧客ヒアリング → 毎週1件
このように、構造図 → 戦略 → 計画の順で落とし込むことで、
思考の流れが「図」から「現実」へと自然に移ります。
4. 戦略と計画は“更新されていくもの”
戦略も計画も、一度つくったら終わりではありません。
実行すれば、必ずズレや発見が生まれます。
それは失敗ではなく、「仮説が現実に触れた証拠」です。
だからこそ、戦略は「守るもの」ではなく「動かすもの」。
現場の変化を踏まえて再構築していくことで、計画は磨かれていきます。
実行の中で起きる“想定外”を、
「想定外だった」で終わらせず、
「次にどう活かすか」に変える仕組みを持つ。
これが、戦略を“生きたシステム”にする考え方です。
💡PDCAの上でOODAを回す ― 二層構造の循環
計画を動かすうえで大切なのは、
静的な枠組み(PDCA)と
動的なループ(OODA)を重ねることです。
PDCA(Plan → Do → Check → Act)
全体の方針と流れを定め、継続的な改善の“基盤”をつくる。
いわば、戦略と計画を支える「大きな円」です。
OODA(Observe → Orient → Decide → Act)
その中で、日々の変化を観察し、即座に判断・行動して微調整する。
現場での「動的な小さな円」です。
つまり、
PDCAが全体の地図を描き、OODAがその中を走る。
大きな循環の中で、小さな判断ループを何度も回す。
この二層構造があると、計画は“止まらない仕組み”になります。
PDCAで方向を保ち、OODAで柔軟に修正する。
それによって、変化の中でも「整って動ける」状態が維持されるのです。
💡循環の設計
計画を立てるとき、最初から完璧を目指す必要はありません。
むしろ「更新することを前提」に設計しておく方が、結果的にブレません。
・初期の戦略は、仮説として“動かしながら確かめる”。
・実行で得た気づきを、次の計画に“循環”させる。
・構造図を見直すたびに、思考と現実が再調整される。
このサイクルが回り始めると、
計画は「管理表」ではなく「成長のリズム」になります。
思考と現実の“循環”を意識して更新を重ねることで、
あなたの戦略は環境に強く、変化に柔軟な“生きた構造”へと進化します。
5. 検証フェーズ ― “実行後の見直し”
計画は「終わらせるため」にあるのではなく、
「次に活かすため」にあります。
実行して終わりではなく、実行したあとに“何が起きたか”を言語化することで、
経験は知恵に変わります。
そのための検証は、以下の3ステップで行うと効果的です。
① うまくいった点を「再現できる形」で残す
成果が出たときほど、
「なぜうまくいったのか」を丁寧に振り返ることが重要です。
「たまたま」ではなく、
「意図的に再現できるかどうか」が、戦略の精度を高めます。
・どんな状況で
・どんな判断をして
・どんな結果が出たのか
この3点を簡潔にメモしておくだけでも、
次に同じ状況に直面したとき、迷わず再現できる型になります。
成功は偶然ではなく、再現できる“パターン”に変えてこそ価値がある。
② うまくいかなかった点を「次に活かせる形」で記録
失敗や停滞は、検証の宝庫です。
ここで大切なのは、“反省”ではなく“抽出”です。
「なぜうまくいかなかったのか?」を責めるのではなく、
「どの要素が影響したのか?」を切り分けて考えます。
・タイミングが早すぎた(または遅すぎた)
・情報が不足していた
・想定外の要因があった
・意思決定の順序がズレていた
これらを整理しておけば、
次に同じ判断をするときに“どこを調整すればよいか”が明確になります。
失敗は、修正の起点。
振り返るたびに、判断の感度が磨かれていく。
③ 改善点を次の計画ブロックに反映
検証は、「終わり」ではなく「次の計画の入り口」です。
再現点と改善点をまとめた上で、必ず次のアクションに“組み込む”こと。
「この流れは維持」なのか
「次回は順序を変える」なのか
「別の手段に切り替える」なのか
改善の意図を、具体的な行動として次の計画ブロックに書き込みます。
これにより、思考と実行の連続性が保たれます。
この3ステップを毎回繰り返すだけで、
戦略と実行の精度が格段に高まります。
日々の経験が「単なる結果」ではなく、
次の構造をつくる“素材”として循環する。
そうして、思考と行動が自然にひとつの流れになっていきます。
6. まとめ ― 思考の構造は、戦略の地図になる
構造化された思考は、戦略の“地図”です。
地図を見ながら進むから、迷っても戻れる。
再設計しながら進むことで、現実と理想の距離が縮まっていきます。
戦略とは、「どこに進むか」を決めること。
計画とは、「どう進むか」を描くこと。
思考を動かし、構造を活かしながら、
“動きながら考える戦略”を育てていきましょう。
次回は、「計画を実行する中で、どう検証し、次に活かすか」。
テーマは、
「動かすことで見えてくる ― 実行と検証のサイクル」
実行しながら整える。整えながら進む。
思考と行動がひとつにつながる“循環の設計”についてお伝えします。
ーーーーーーーー
【関連記事】
過去記事:「焦りを手放し、心と思考を整えるーー 何もしない時間が未来を動かす理由」
「 “整った自分”で選ぶ ― 納得に基づいて次の一手を見極める」
「 “整った自分”で決める ― 戦略としての決断を形にする」
外部記事(note):「思考をかたちにするーー見えることで、動き出す」
*
*
オンライン相談
オンライン相談
1回90分 11,000円 いまなら5,500円(税込)
ひとりで考えていても答えが出ない。けど、相談できる相手がいない・・・
そんな悩みを、気軽にご相談ください!
・申し込む前に、もう少し詳しい情報が欲しい
・自分のケースが当てはまるのか知りたい
など、ご要望のあるかたは、『お問い合わせフォーム』から、お気軽にご連絡ください!